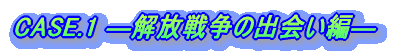
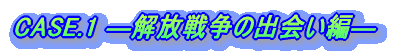
(P8)
CASE・1~祈り~
グレミオが復活した時のデュオンの異質さに気付いたのは、ほんの少数。
そして、〝彼〟もその一人だった。
元竜騎士見習いのフッチは、デュオンを見かけるなり声をかけた。
「嬉しく、ないんですか?」
「……え?」
デュオンは振り向く。
「グレミオさんのこと……、かえって辛いんですか? 失くしたものを、思い出させるから」
そう、デュオンはあの時、どこか辛そうな表情を一瞬だけ見せていた。
デュオンはフッチに眼を向け、
「……何か聞いた? テッドのこととか」
「……はい 」
「そっか」
デュオンは納得した風で、フッチは言い募る。
「でも……デュオンさん、そのために今あるものまで失わないで下さい。あなたは幸せになったっていいんですよ?」
「――――僕に、その権利があるとでも?」
沈黙の後の言葉は、どこか乾いた響き。
「あなたが、僕達のために祈ってくれたように、僕達もあなたのために祈ってるってことです」
「僕は……」
反論しかけた言葉を押し留めるように、フッチは言葉を継いだ。
「戦ってくれたじゃないですか、僕達と……竜のために。それって、祈ってるってことなんでしょ?
あなたにとって、誰かを……皆を守るためだから」
「僕は――何も守れていない 」
言葉にした後、失言に気付いたように、少し眉をしかめた。
「……ごめん。こんなこと、言うべきじゃないね」
少なくとも、リーダーとしては。
「いいえ、僕も――同じですから」
「――ごめん 」
「…………」
再び繰り返す彼にフッチは悼むように沈黙を返した。
「……君は、なぜグレミオだったのか、解る?」
「え」
「疑問には、思わない?」
それは、多分――。
「君が、選んだからだよ」
声はふいに違う方から降った。
「――――僕が、選んだ?」
どこか、遠い眼差し。
視線だけ、そちらに向ける。
「星は……君と宿星、両方の意志があってはじめて集う。君は……百八星を揃えずにいることも出来た。なぜ集めたかなんて聞かないけど、これは、君が選んだ結果だよ」
淡々とした口調で、ルックは言葉を紡ぐ。
それに対して、彼は。
「僕は――彼等の願いを無駄にしたくなかっただけだ 」
それは人を率いるものの表情。
「レックナートに認められるためじゃないし、ましてや何か期待した訳でもない」
「……うん 」
知っている。
誰かを百八星と門の紋章の力で生き返らせることなど、期待などしていなかったと。
「…………」
デュオンはルックを見遣った。――淡々とした瞳。
彼が肯定する言葉を出すのは珍しい。
フッチは疑問を投げかける、デュオンに向かって。
「でも本当に……それがあなたの願いだったんですか?」
「何?」
「その人達が、生きて……いてくれることが、あなたの願いだったんじゃないですか?
……僕にはなぜグレミオさんだったのかは解らない。
けど、解るのは、それが、あなたの願いで、僕らはそれが叶うのを願ったということだけ 」
「――――――」
惑う様なデュオンの沈黙に、ルックはため息をついて。
「忘れたの? 自分が言ったくせに。〝彼〟が死んだ時に言った言葉」
視線だけ、彼の方に向けて、
「――――何だっけ 」
「あいつがいないだけで世界が違って見える。自分が知ってる世界は全て〝彼〟を通した物だったって」
その言葉に、思い当たる感覚。
「……それって……僕にとっての竜洞や、ブラックと同じ……?」
「……そう、全ての〝始まり〟だよ、……その人にとってのね 」
「――――」
フッチはルックの言動が意外で、思わず彼を見詰めた。
――――よほど 親しいのだろうか?
ふいに、彼の声が流れた。
「――――それで、許されるのかな、……僕は 」
自分勝手な願いのままで。
「……許されますよ」
「君の願いは、君の物だよ。まぁ、僕は……誰が何を願おうと知ったこっちゃないけどね」
その言葉にフッチは、何気なくルックに疑いの眼を向けたが、
デュオンはフッチとは違い、ゆるく、微笑み、
「……そうだね、……ありがとう 」
「鬱陶しいのが嫌なだけだよ」
そう言い捨てると立ち去ろうとする。
「――ルック! グレッグミンスター突入の時、君も付き合ってよ」
その背に投げられたデュオンの声に、
ルックは肩ごしにこちらを見て。
「それが命令なら、仕方ないね 」
それだけ言うと、去って行った。
「…………」
フッチはその態度に違和感を感じた。
彼をリーダーとして扱っているように見えながら、誰よりもそうじゃない気がしたのだ。
「……デュオンさん。彼は……かなり前からエレメント城に?」
「ん? まぁ……割に初期の頃からいるけど……何か?」
「……仲が、いいのかと思って」
「……僕と? ……どうかな 」
「彼にしては、親切に見えましたけど」
そう言うと、デュオンは少しだけ眉を寄せて。
「そう? ……困ったな 」
「え? 何でですか?」
その問いには徒首を振って、デュオンは話題を変えた。
「いや……それよりさ、そんなにかしこまらなくていいよ。〝あの時〟みたいに話してくれると、こっちも楽だし」
それは戦争前、魔術師の塔にデュオン達を送るために最初に出会った時のことだった。
「え……と、でも 」
デュオンは軽めの口調で、
「あんまりいないんだよね。ふつうに話せる人。ま、無理にとは言わないけどさ」
「いえ……別にあなたがリーダーだからとか言う訳じゃなくて……」
フッチがためらうと、僅かにデュオンの表情がやわらぐ。
「まぁ……解るけど、君だって幸せになったっていいんじゃないかな」
「…………」
不思議な人だと思った。
「――――あんな僕で、いいんですか?」
「あんな、じゃないさ。明るくて、元気があって、自信があって――――真っ直ぐな眼をしていた」
「……だけど、そのせ――」
デュオンの手が、その言葉をとどめた。
「――――やったのは、ウィンディだ。俺は、確かめに行く、――真実を。
君も、付き合うだろ? 最後まで」
「――はい、勿ろ――いや、当然だよ……!」
あの頃を思わせる瞳でフッチは答える。
「このまま、終わりになんかしない」
「それは、同感だな」
デュオンは軽く右手を掲げた。