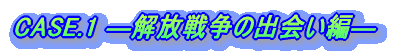
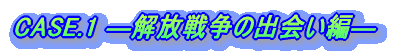
(P7)
〈彼〉を失くした時の
闇い闇い瞳。
まるで光る様に。
その時、『彼』はもう戻らないと思った。
CASE・1~喪失~
「何してるの」
デュオンは城の片隅で湖を眺めていた。
「別に……、この城にいる大半はテッドのこと知らないし、気ぃ使って欲しくないから」
「別に僕は 君がどうしようと 構やしないけどね」
「……ルック 」
デュオンは身を起こすと、拳を握り締める。
「僕は……あんな別れ方をするために、もう一度逢うことを望んだ訳じゃない。
僕は、あれを、どうしようもなかったとは絶対に思わない! 絶対何かあった筈なんだ……方法が」
一瞬、眼を細める。
「あの時、逃げなければ良かった。例え、この紋章の力を使ったとしても……!」
それは、言っても仕方のない、デュオンとルックが城で再会する以前のこと。
ルックはその時の詳しい状況など、知りはしなかったけれど。
「さらに最悪の結果になってたんじゃない? じゃなきゃ あんたは……逃げないだろ?」
「――そうかもな 」
――継いだばかりの紋章の力を、屋内で使ったところであの状況を打破出来なかったかも知れない。
最悪、自分や味方も含めて瓦礫の下か、ソウルイーターの餌食ということさえあり得た。
まして当時はソウルイーターの危険性を知らずにいたのだ。
「だけど……何もせず逃げた俺は、……やっぱり卑怯だ」
デュオンの思い詰めた口調とは対象的に、ルックの静かな声。
「運命だったとは、思わない?
君と彼が三百年の時を超えて出会ったことも、紋章を受け継いだことも、彼が……命を賭したことも」
ルックの瞳は、冷たい程の色を湛える。
「確かに、悪いことだけじゃなかった。だけど、それでも……俺は、あれを運命だったなんて、言わない。
仕方がなかったとは言わない。絶対に……!」
思い詰める程の、鋭い 眼差し。
――目の前で、手が、届かなかった。
ルックの脳裏に、かつてのデュオン達の姿が過る。
「……起こってしまったことは、仕方ないと思うけどね……」
ルックはふいにため息をつく。
デュオンのような考え方は、自分を追い込むだけだ。
しかしデュオンはゆるくかぶりを振って、
「出来ないよ……ルック」
「……え……」
ふいにもたれかかって来たデュオンを、ルックは支える形になる。
「……戦えない僕なんて、誰もいらない……」
ルックは微かに反応して、デュオンの方を見る。
肩に置かれた手が微かに震えて力が込もる。
「だから……これが最後だ」
ルックの肩に頭を預けたまま、キッパリとつぶやく。
「もう、振りかえらない。……決着がつくまで」
「…………」
鋭い眼差しのまま、横をすり抜けて立ち去るデュオンを、ルックは微かに眉根を寄せて見送る。
デュオンが立ち去った後、
「……手間の掛かるリーダーだな……」
そうつぶやきながら、内面の微かな魔力の高まりには気付かない。
その理由など知る由もない。
自分も、戦ってもいいと思いはじめていたことなど気付く筈もなかった。
CASE・1~理解者~
「……眠りなよ」
ルックが声をかけると、無表情とも取れる瞳がこちらを向いた。
「ずっと寝られてないだろ」
その言葉に微かに眼が見開かれる。
「バレてるよ、気付かないあいつらの方がどうかしてるよ」
微かに微笑むように、デュオンの緊張が解ける。
(そうか……なんだ、バレてたんだ )
デュオンはふいにルックに近寄るとその肩に凭れかかる。
「……おやすみ……」
言葉と同時にそのままズルズルと崩れ落ちた。
「ちょっ……」
半ば支える様な形で、ルックは床に膝を落とした。
「……ここで寝る気か……? 」
眉をしかめた苦い調子の言葉に、しかしデュオンは反応しない。
(まさか未だ寝てる訳じゃないだろ)
微かに青ざめて見える彼の様子に、ルックは不機嫌に言葉を飲んだ。
『こんな状態、全く誰が知るって言うんだろう』
今までは、〝彼等〟 がその役目だった筈だ。
けど今は……。
今は偶々、自分がそれを看破したに過ぎない。
――こんな状況、予測していた訳じゃない。
自分にとって、ここは単なる憂さ晴らしの場所で、もう少し楽しいかと思ってた。
自分がもし、この場所で死んだとしても、それはそれだけのことだ。
受け入れる覚悟はあった。
「………………」
ルックは暫くそのままデュオンに視線を落として動かずにいたが、やがてその姿は、風と共に消えた。
「……ったく 」
デュオンの部屋のベッドの真上に違わずテレポートを果たし、
デュオンをベッドに収めると、ルックはベッドの脇に降り立つ。
仮にも軍主の部屋が窓際で、大っぴらに外に面しているのもどうかと思うが、今度ばかりは助かった。
風の通る場所でなければテレポートしにくい。
ハッキリ言ってデュオンはかなり重かった。
ため息をつき、デュオンを一瞥する。
「……」
意識的無意識。
意識と無意識の狭間、
心の底で、微かに同情に似た気持ちを感じる。
それは認められることも、口にすることもない。
ただ彼の顔を一瞥すると、ルックは静かに部屋を後にした。