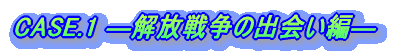
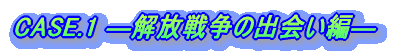
(P6)
CASE・1~世界~
グレミオが死亡した後、
デュオンは極力普通に振るまってはいたが、ある時ふと、漏らしたことがあった。
「……何が変わったかは、解ってるつもりだ。
グレミオがいなくても、やっていけると思ってたよ。むしろ、鬱陶しいくらいだったのに」
少し自重気味な言葉で、空を見上げた。風が吹いていく。
「―――何でだろう、世界が……違って見える。
……思えば、僕の知ってる世界ってのは、全部グレミオを通したものだった。
彼が、ずっと教えてくれていたんだ。ずっと変わらないと思ってた。何が、変わったとしても」
国を、立場を、変えたとしても。
上を見上げていたデュオンは、微かに笑ってルックの方を見た。
「反則だよな、あんなこと言うなんてさ」
――坊っちゃんは最後まで信じることを貫いて下さい――
あんなことを言われては、何も言えない。
一方ルックは訝るように顔を向けた。
『あんなこと』と言われても、自分は知らない。同行していなかったから。
常にパーティに在る訳では、勿論ない。
そんなこと、デュオンの方も、当然知っている。
そしてルックは人を小馬鹿にした口調で言う。
「僕が知る訳ないだろ? あんた、あんな馬鹿の言ったこと、気にしてる訳?」
「馬鹿って……」
少し呆れたようなデュオンに向かって言葉を重ねる。
「だってそうだろ?あいつが勝手についてきて、勝手に選んだんだ」
「だからって……!」
その言葉を、遮るように。
「何言ったか知らないけど、どうせあんたを立ち止まらせまいとしたんだろ。
けど、あんたが 何を失くしたのかも気付けないようじゃ、見事に失敗だね」
「……何を、失くしたって?」
デュオンはあえてルックに問いかけた。
「〝世界〟なんじゃないの?」
デュオンは少し意外そうに息を呑んだ。
「…………そう、かも知れない。それって、普通のこと?」
「別に……」
〝普通〟など知らない。徒、
「誰にだって そういう存在が在たって、おかしくはないよ」
多少投げやりなセリフの中に、ルックの理解を感じる。
デュオンはあえて何も言わずに立ち上がった。そして、一言。
「ルック、ありがと」
結局デュオンは人前で哀しみを見せはしなかったけれど。
その日以来、ほんの少し、ふっ切れた顔をしていた。
CASE・1~望み~
父親であるテオ・マクドールとの一騎討ち後、デュオンは再び石版を訪れた。
帝国に追われ、解放軍に加わり、その任を継いだ時から 予測はしていたのか、
デュオンの瞳は 深い色を湛えてはいたものの、比較的、落ち着いて見えた。
「ルック、聞いていいか?」
「何 」
「この紋章……父さんが死んだ時、グレミオやオデッサが死んだ時も反応してた。何か……知ってるか?」
右手を軽く掲げる。
「さぁね。でも……予測ぐらい出来るんじゃない? どんな時、それが疼くのか考えてみなよ」
「人が……死ぬ時……だね。それも、僕の傍にいた人が」
「なら、答えは解るんじゃない? その紋章は……君の傍に在る人間の『死』に反応してる」
(そして魂を喰らい、力を増してる)
その言葉は口にはしなかった。
デュオンは浮かない顔で予測を口にした。
「まさか……あの時、魂を……勝手に喰った……?」
「僕は現場を見てないから、断定は出来ないよ。けど、ソウルイーターには、敵も味方もない。
今までにも大勢喰ってしまったんじゃない?」
「どうして……」
「自分で考えなよ。それより君にそれを御することが出来るのかい?
出来なければ、それは……際限無く魂を喰らうよ 」
デュオンは少し呆れた様に言う。
「予測はしてたけど、随分ハッキリ言うよね」
「悪い?」
「いや……だから聞いたんだけど 」
「……」
デュオンは改めてルックに訊いた。
「どうすれば制御出来るんだ?」
「魔力と精神力」
「気付いてたなら、言ってくれりゃ良かったのに」
「何で」
言った所で何が変わると言うのか。
「何でって……気構えが違うだろ」
「へぇ……」
「味方の足引っ張ってたら洒落にもならないよ。――まぁ気を付けるよ」
デュオンは一度、言葉を切って、
「……それにしても、テッドがいた時、俺、喰われた奴見たことないよな。
やっぱ三百年の付き合いだから? それとも気付かなかっただけか……解らない……。
俺、本当テッドのこと、何も解ってなかったんだな。多分、今も同じ。
――そんな俺の傍にいるの、辛かったんだろうな……」
「でも、あいつは選んだんじゃないか 」
「?」
デュオンはルックを見つめる。
「僕は、あいつが真の紋章を宿す身でありながら、人といることを選んだのだと思ったよ……」
「…………」
ルックが言葉を続ける。
「言っておくけど、真の紋章の継承なんて、そうそう起こることじゃないんだ。
もし、あいつが、自分の意志で、その紋章を君に渡したのなら。
君 それだけ信用されてたんだろ」
ふてくされたような言葉にデュオンは眼を閉じた。
「君が言うと説得力が違うな。……気休めなんて言いそうにないから、却って安心するよ」
「頭、おかしいんじゃない?」
「そうかな、……ルック、僕はテッドを助けたい」
真っ直ぐに眼を見据えて。
「死んでんじゃないの?」
ストレート過ぎるセリフに 少しばかり震えたけれど、
それでも、ハッキリと告げた。
「いや……生きてるよ」
揺るぎない言葉。
「何で」
「勘……かな……」
「馬鹿じゃないの? ――そう思うなら勝手にしなよ。うだうだ考えてないでさ」
「……解ってる」
突き放した様なルックの言葉に、デュオンはようやくいつものように顔を上げる。
「そのために、選んで来たんだ」
その言葉に、朋友への想いを感じた。微かにざわめくような気持ちに、ルックは少し眼を伏せる。
「まさか、そのためにここに……?」
少し嫌そうに言うと、デュオンは明るさを戻した瞳を向けた。
「理由は、一つじゃないよ。けど……僕の『望み』はそれなのかもな 」
ルックはため息をつく。
こいつは自分が知っている世界とは酷く違う。
――ま、好きにすればいいさ――
心の底でつぶやくと、髪をかき上げた。