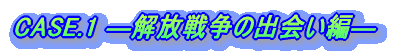
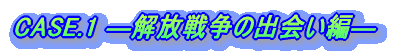
(P5)
CASE・1~食事~
二人は、珍しく、夕方の空いた食堂で食事をしていた。
この時間帯に食堂が空いていることが珍しい訳ではなく。
自分が食堂にいるのが珍しい訳でもない。
唯、ルックが食堂での食事に同席している。
それだけが、珍しい。
デュオンは向きあった席にいるルックに眼を向ける。
ルックは、基本的に、人といることを好まない。
人に偉そうにちょっかいかけたりする割には、単独行動が多く、騒がしいのは嫌いらしい。
今回も、人が少ない時間帯と言うことも理由の一つにあって、了承してくれていた。
その他の理由としては、デュオンが度々誘うからか。
気まぐれっぽく、OKしてくれた。
「――――」
いつも、思っていたが。
遠征中でも、本拠地でも、ルックが美味そうに、とか、楽しげに、食べてる所は見たことがない。
どー見ても、美味しくなさそうに、と言うか、ぶっちゃけ不味そうな顔をしている。
誰かに嫌味言ったりする時は別だけど。
そーいう時は特有の意地悪っぽい笑みを浮かべる。
だけどこれじゃあ、食べる楽しみとか半減――いや、三分の一位なんじゃないだろうか。
「不味い? それ 」
つい、聞いてみる。
「まぁね」
「ふーん、食べてみていい?」
ちょっとした興味でそう言うと。
「欲しいならあげるよ」
ルックは小鉢を差し出す。
受け取って、食べてみる。
「うーん、別に不味くない」
むしろ、その逆だ。
「僕には不味いよ」
「…………」
味覚が違うのかな。
それとも好みが違うだけか?
魔術師の塔での食事って、あまり想像つかないけど、美味しいと思ってたんだろうか。
「魔術師の塔での食事って、美味しかった?」
「嫌いだよ」
――参考にならないか。
「じゃあ、これは?」
デュオンは、運ばれて来た特製シチューを差し出す。
今日はグレミオが厨房にいるため、特別製だ。
「あんたのだろ?」
「構わないって、食べてみてよ、ちょっとでいいから」
そう言うと、ルックは仕方ないなぁ、とつぶやく。
「どう?」
「……別に……」
ルックの表情は相変わらずだ。
というよりむしろ眉間に皺が寄ってないか?
「うーむ……」
デュオンは思案する風にルックを眺める。
夜。
静まった食堂をルックが通りかかると、奥で人の気配がした。
「……」
こんな時間に誰が、と言う疑問は一瞬後には解けた。
ソウルイーターの気配。
未だ押さえ切らぬ気配が滲み出ている。
彼の気配も同じ。
もっとも、こちらは押さえようともしていないのだろうが。
恐らくは、気付いてはいない。
自らの紋章が放つその気配にも。
その、魔力にも。
制御し切れぬ強い力に、漠然とした不安は感じてはいても。
(……未熟だな)
デュオンがこちらに気付く。
「ああ ルック、ちょうど良かった」
「あんた、何やってるのさ」
大体予測はつく。
「息抜き。――食べてみてよ」
持っていた鍋から、スープらしき物を皿に盛り付ける。
「何、大丈夫な訳?」
「まぁね」
とは言え、見た目はそう悪くない。
まぁ いいかと 気まぐれ程度に そう思って。
席につき、味見する。
「!!!」
一口、口にした瞬間、ルックの顔色が変わり、
ガタッ!
音を立てて立ち上がる。
――突き抜けるように、不味い……!
「不味ッ……最悪ッ……!」
半ば咳き込みそうになる。
見た目では解らなかった、不覚だ……!
デュオンは、驚いた風もなく、眼を見開いて。
「なんだ、味覚ない訳じゃないんだ。……良かった」
「な……!」
(何だって……?)
彼は悪びれもなく続けた。
「だって、いつも不味そうにしてるから。ひょっとして、味覚がないんじゃないかと。でも違うんだね、安心したよ」
(そんな訳あるか!)
「ふざけないでよ……!!」
バンッ!
思わず叩いた机の音と同時に。
大気を切る風が、デュオンの頬をかすめる。
僅かに、血の色が滲む。
デュオンが身を引かなければ、スッパリいっていた筈だ。
――向けられた、純粋な怒り。
デュオンは驚いたように、それを見ていたけれど。
「僕は、僕なりに真剣だったんだよ。――ありがとう」
「……!?」
解らず、眉を寄せる。
「怒っただろ? 本気で 」
「当たり前だろ!」
「だからだよ。何だか、新鮮だ」
(は……!?)
「初めてかも知れない。こんな風に純粋に怒ってくれる人って 」
「……」
デュオンは、笑っていた。
「何――言ってるのさ。怒る奴くらい幾らでも居るだろ」
怒りつつ、多少冷静にそう言うと。
「――違うんだ、少し」
「何がさ」
「純粋に、僕に対して怒ってるっていうのとはさ」
(――?)
益々訳が解らない。
「――親友殿は? フリックだって怒ってたろ? ――大人げもなく」
そう言うと、デュオンは微かに笑う。
「フリックのは、八つ当たりだよ。テッドは……本気で怒ってるって言うより、僕を近付けさせないためって言うのがほとんどだったし――確かに怒ってはいるんだけど、少し、違うんだ。相手のためにやってる――みたいで」
微かに切な気に笑う。
だとすると、付き人連中も除外か。
「――じゃあレパントは?」
「あれは別に僕に怒った訳じゃないだろ。会うためとはいえ、銘刀キリンジを盗られたからだし」
「まぁね」
「でも君は、本当に僕自身に対して怒ってた」
「そんな大層な物じゃないだろ、あんた誰にでもこういうことする?」
してないだろうね、僕と違って。
――予想通り、彼は頭を横に振る。
「いや……でもやったとしたら、みんな、君みたいに怒ると思う?」
「…………」
怒らないかもしれない。あの連中なら。多分、本気では。
「普段は、こんなことしようとは思わないんだ。まぁ、めったに。
だけど、あの時――君に味覚があって不味いのか、それとも本当にみんな同じようにしか感じてないのか、
気になって、確かめたくてさ、……知りたかったんだ、ゴメン」
「ハタ迷惑だよ」
「うん」
デュオンは片付けはじめる。
「これさ、テッドに色々教わってた時、偶然、開発してさ、二人とも苦しみまくって、その後、大ウケしたよ」
「だからって、僕を巻き込まないでよ」
迷惑だと、言外の意味を込めて言うと。
デュオンは微かに穏かに苦笑した。
「直接聞こうとは、思わない訳。――答えるとは限らないけどね」
デュオンはゆるく首を振った。
「多分、駄目だったと思う。――例え君が〝味覚がある〟 って答えてくれたとしても、実感として、納得出来なかった」
「――そんなに、何も感じてない風に見えるとはね」
微かに、内面が震える。
そんなに、何も感じない人形のように見えているのか?
「ううん、徒、食べてても楽しくなさそうに見えてた。だからさ……」
デュオンはそこで言葉をつぐんだ。
「――だから?」
先を促すと。
「う……ん、これ言うとますます怒りそうだけど」
「今さらだろ、言わなきゃ切り裂きだけどね」
「……解った、どっちでも同じなら、言うよ」
デュオンは、ルックを見据えた。
「あんまり何食べても不味そうにしてるからさ、本当に、本気で不味い物食べさせたら、どうなるだろうと思って。
――少し、興味でわくわくしてた」
ゴッ!!
瞬間、風の刃が轟音と共に壁をえぐる。
「フン、馬鹿らしいね」
悪意の込もった笑みを向けると、
デュオンは本気で緊張していたらしく、息をついて。
それでも、笑顔を向ける。
「ああ、でもそうだな……、思えば、あのシチューの時は、〝不味い〟って言ってはいなかった訳だし……」
又何か言い出すのかと斜に視線を返せば。
「探せば、ルックが美味しいって言う物もあるんじゃないかとおもってさ」
あるわけ、ないだろう。
大体、ルックの辞書に、美味しいという文字はない。
軽く息をついて、
「下らない、帰らせてもらうよ」
えぐれた壁をそのまま、
ルックはさじを投げたように踵を返した。
――全く、気まぐれなんか起こすんじゃなかったよ。
あいつにちょっかい出すとこっちが疲れる。
思えば、油断していた。
夕方、あいつに薦められたものが、不味かった訳じゃなかった。
だからかも知れなかった。あんなのに、引っかかるなんて。
馬鹿らしい。
そう、別に不味かった訳じゃない。
あの時、顔が歪んだのは、不味かったからではなかった。
徒、
そぐわない、と、
そう 思っただけで。
自分には、そぐわない。
なのに なぜ。
あいつのは、――違う気がした。